話し合いに参加してほしいと願う。
午前中の視察は、折り返し点の下砂橋までと進むが、この途中で川の水面をかすめるように、素早く飛んで行ったカワセミを認めることができた人は幸運であった。わずかでもきれいな水があり、そこに小魚が棲むことができれば、いくらでもカワセミに出会えることを保証したい。
午後の第2部は、定刻の1時に開会され、尾崎市長のあいさつの後、プログラム通りに、国交省国総研主任研究官中村圭吾氏による「多自然川づくりについて」、都が不参加となったため私が行わざるを得なくなった「空堀川(下砂橋~東芝中橋)の整備に関する懇談会まとめ案の報告」、多自然川づくり研究会の吉村伸一氏よる「空堀川のいい川づくり」と進んだ。いずれもパワーポイントを使った映像を多用した説明であったが、短時間のため十分に伝えきらなかったところがあったかも知れない。 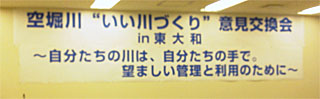
参加者の川に対する知識レベルはマチマチであり、何回もこのような機会を繰り返さないとレベル合わせは難しい。
これも民主主義にとっては、ジェネレーションギャップとともに克服を迫られるところである。(写真は会場に貼られた横断幕)
さて、意見交換会はその名のごとく、最終段階のパネルディスカッションへと進んだ。多くの意見が出された。都の案である現河川の殆どを埋めて緑道とする案に賛成する者。そうでない者。
下流の整備が終わった東村山市民からは、整備の仕方によっては流れが下流まで届かず途中で涸れることへの心配と、緑道となった旧川の悲惨な姿も語られた。上流の武蔵村山市民からは、東大和と同様な川づくりが何をもたらすかと心配する声も挙がった。川は連続し上流下流が相互に影響し合っていることを再認識する発言であった。参加者皆さまに感謝し、今回の報告と致します。
参加者アンケート結果は、まとめが完全に終わっていないが、速報としてし次ページに掲載いたします。 |